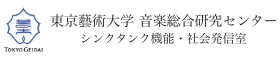音楽家の『コミュ力』アップ大作戦③(『若手音楽家のためのキャリア相談室28』)
箕口一美
1. 畑中良輔さん、吉田秀和さんの訃報に接し、想うこと
(本稿は2012年『ストリング』誌7月号に掲載された記事の改訂版となります。)
「4月は一番残酷な月」――T. S. エリオットの詩「荒地」の、とても有名な冒頭です。でも、今年に限っては5月もまた残酷な月。20世紀後半の日本のクラシック音楽を、文字通り、作り上げていくのに力を尽くした二人のおじいさまが世を去りました。
畑中良輔さんと吉田秀和さん。
新聞や雑誌に特別寄稿や特集が組まれることでしょう。直接知らない、自分とは関係ない昔の人たち、と思わずに、どんなことに取り組んだ人たちなのか、この機会にぜひ知ってください。わたしたちが当たり前だと思っている仕組みや状況を作った人たちです。どうして、どんな思いで、クラシック音楽を取り巻く状況に変化を起こしてきたか、ぜひ興味を持ってください。人が亡くなるのは悲しいことですが、その人の一生を改めて見つめるきっかけにもなります。
逝く人が残る人々のために最後に果たしてくれる役割は、親しい人たちの言葉や追悼記事を通して、その人の生きてきた姿を見せてくれること。それを見て、わたしたちは逝ける人の最後のメッセージを受け取ることにもなるのです。
Ars longa, vita brevis(芸術は長く、人生は短い)――クラシック音楽という永遠のロングセラー(それをまさに『古典』というのですけれど)と付き合う人間にとって、先達たちの取り組みは、自分たちの生き方に直結しています。あなたのキャリアは、彼らの積み重ねの上に築かれていくものでもあるのです。短い人生を繋いで、芸術の永遠を語り継いでいく――わたしたちはお二人の後ろ姿を見送りながら、何を受け取るでしょう。
2. 何が起こって欲しいのか――「aha!」の瞬間
さて、「コミュ力アップ大作戦」は、今回も「いま思っていること、それはなんだ?」-whatを課題に練習を重ねていきましょう。
その前に、「小さな本番」について、もうひとつ押さえておきたいことがあります。聴き手がどんな人たちでも(小学一年生でも、90歳過ぎたお年寄りでも、クラシック音楽は趣味じゃないと思っている人たちでも、興味津々の人たちでも)、これを起こすことが出来れば、音楽家がそこで演奏してよかった!となること――それは「aha!」の瞬間を経験してもらえることです。「Aha!」――日本語にすれば「へえ~、そうなんだ!」「納得!」「なるほど!」です。英語で相手がそう言ってくれたら、「そうそうそう! そうなんですよぉ」とこちらも嬉しくなってしまうような、そんな状況で使われる言葉です。
何かもやもやとしていたのが、さーっと霧が晴れるように掴むことができた瞬間の喜びを経験したことがあるでしょう。「わかった」「理解できた」という言葉だけでは表せないような、気持ちよい経験だったはずです。脳で理解した、というよりも、五感で受け取ったような感じ。何というか、すとんと心の中に落ちてきて、納得してしまう。
それを「実感」と呼んでおきましょう。実感できたものは、活きた知識、自分で使いこなせる知識になります。同じ知識でも、ただ暗記したり、受け身で聞いたりしたこととは違う豊かさがあるのです。
コーディネーターとして、初めて兵庫県の山間部の小さな小学校の一学級で行った「アウトリーチ」――そこでもし「あのこと」が起こらなかったら、今のわたしはいなかっただろうと思える「奇跡」(とその時思いました)が起こりました。
曲はエルンストの「《魔王》の主題による大奇想曲」、演奏は高木和弘さん。ピアニストのスケジュールが合わず、彼はいきなり無伴奏で小学校4年生へのアウトリーチを行ったのでした。この曲がプログラムの最後でした。魔王の物語を一通り話した後、この超絶技巧の作品に一気にのめり込んでいったヴァイオリニストの気迫は子供たちにもしっかり伝わっていました。子供が息絶えたことを告げるピチカートが弾かれた瞬間、ひとりの男の子が「あ、死んだ。」と呟いたのが聞こえました。そんなに大きな声ではなかったので、みんなそれほど集中して静かに聞いていたんだと改めて思ったくらいでした。その声に応えるように浮かんだ高木さんの会心の笑みが忘れられません。
この男の子にとって、あのピチカートが「aha!」の瞬間だったのでしょう。思わず声に出てしまったくらい。音楽が物語を伝えてきたのを彼はそこで実感したのです。
この話は、もうあちこちで繰り返し話しているので、あ、またか、と思われるかも知れません。でも、「小さな本番」で一番大切なのは、真剣勝負の演奏でこういう実感をもたらすこと、そして、そんな演奏に向けて、聴き手がすとんと納得できるような工夫をプログラムに施すこと。どちらも、あなた自身が音楽家として持っているものを精一杯活かしていくことが求められます。つまり、音楽で伝えたいという強い思いと、それを伝える技倆と表現力です。それも重要な「コミュ力」であることをここで確認しておきましょう。
「あ、死んだ」と呟いた男の子ももう20代半ばになっています。もしかなうなら、大人になった彼に話を聞いてみたいものです。蛇足ながら、こういう経験をさせてくれたアーティストを、一緒に仕事をしていた人間は一生忘れません。高木和弘の一つのピチカートが、その後少なくとも3人の生き方を変えています。
3. クァルテット・セレシアが「今思っていること」
やっと今号の本題に入ります。まずは、クァルテット・セレシアが、小学校一年生のための小さな本番を依頼されて作ったプログラムを見てみましょう。
ブラームス:ハンガリー舞曲第5番
シュトラウス:ピッチカート・ポルカ
カエルの歌
ボッケリーニ:メヌエット
アンダーソン:猫のワルツ
ブラームス:弦楽四重奏曲第2番 第4楽章
アンコール:J. シュトラウスⅠ:ラデツキー行進曲
これだけ見ても、プログラムの意図はほとんどわからないでしょう。しかも最後にはブラームスの弦楽四重奏曲がまるまる1楽章どーんと控えています。これが小学校一年生向け?
少し説明を加えましょう。
まずは、アンダーソンの「猫のワルツ」。これは子供たちが使っている教科書にも出てくるし、授業で聞かせたことがある、という情報を先生からいただいていました。
こういう事前情報はとても大切です。このプログラム実施にあたっては、受入校とアーティストを繋ぐ役割を担う人(そういう人のことを、コーディネーターと言います)が、室内楽アカデミーのスタッフと綿密な打ち合わせを行って、Qセレシアに伝えています。こちらのスタッフも打ち合わせ内容をきちんと定型のシートにするという手順を整えています(こうしておくと、打ち合わせておくべきことの漏れを最小限におさえることができます)。ただ、そんなスタッフによる支援体制ができあがっている「小さな本番」の現場は、まだまだ少数派ですから、普通はこうした手間をアーティスト自身がかけていく必要があることを肝に銘じておいてください。
聴き手についてきちっと取材してプログラムを作る。
これは21世紀を生きるプロの音楽家の基本のひとつです。
プログラム全体が「踊り」の音楽で構成されていることにも気がつくでしょう。これもやはり先生からの情報で、うちのこどもたちはリズム感覚がどうも弱い、三拍子や四拍子の区別がついていないみたいだ、と聞いていたので、そこをサポートする内容を盛り込んでみた結果です。
選曲にあたっては、「子供たちがこれから間違いなくまた聞くことのある作品」を念頭においています。名曲と呼ばれる曲は、繰り返し耳にする機会が多い作品のこと。でも、それは音楽家の方も努力して、聞く機会を増やしていかなければ、忘れられてしまいます。名曲を名曲であり続けさせる責任を果たしていきましょう。
そういう曲ならば、子供たちも聞いたことがあるかも知れません。すでにどこかで聞いたことがある、というのは、子供たちの「知的満足感」(あ、それ知ってるよぉ)を刺激して、プログラムへの集中を高められる効果があります。先生は十中八九、プログラムが始まる前に、「今日はクラシック音楽の演奏を聞きます」と言って、いつもより難しいことが始まりそうな前振りをするので、子供たちはそれなりに緊張したり、身構えたりしているのです。そこへ、自分も聞いたことがある「クラシックの曲」が演奏されると、「お、自分もなかなかちゃんと知ってるじゃないか」という子供なりの自負心がくすぐられます。これは実はとても大切なことなのです。別に大げさに褒めてあげなくてもいい。知ってるよぉ、という声が挙がったら、嬉しそうな表情で、ありがとうと返しましょう。子供たちと演奏者の間の共感の絆が一気に強まります。
ただし、ここで注意したいのは、知っている曲なら何でもいい、というわけではないこと。「クラシック」を選びましょう。子供たちが少し背伸び出来る、背伸びをした実感を持てる選曲が大事。おのずと、どんな曲を選んではいけないかは、分かりますね。
ところで、なぜ最後にブラームスの弦楽四重奏曲なのでしょう。
それは「それが今クァルテット・セレシアが一生懸命取り組んでいる曲だから」。 学校の先生から取材し、子供たちの背伸びを後押ししと、聴き手が必要としていることにしっかり耳を傾けながら、自分たち自身が課題としていること、今自分が一番聞いて欲しいものを聞いてもらえるようなプログラムを構成する――「小さな本番」があなたのコミュ力アップに繋がるための、ここが勘どころです。Qセレシアが作ったプログラムのテーマは「ブラームスを聴かせたい」なのです。
ボロメーオ・ストリング・クァルテットのヴァイオリニストであるニコラス・キッチンが、トリトン・アーツ・ネットワークのアウトリーチに協力している若い音楽家たちとのディスカッションで言っていたことが印象に残っています。「自分が今一番真剣に取り組んでいる曲が、一番聴き手に伝わるものだ。だからアウトリーチでもそういう曲を演奏するべき。よくさらっていない曲を弾いても、相手には何も伝わらない。」
彼は実際、保育園でベートーヴェンのラズモフスキー第3番やバルトークの4番を弾いて、大喝采を受けていました。どちらも、そのとき来日プログラムに入っていた作品ですから、確かに一番さらいこんであるものばかり。このディスカッションの記録は「児玉真の徒然」というブログ読むことが出来ます(2012年2月19日のエントリー)。他にもとても参考になることがありますので、一読をお勧めします。
ブラームスを小学校一年生に聴いてもらうために、いったいどんな工夫をしたらいいだろうか。Qセレシアの4人にとって、その問いかけはつまるところ「弦楽四重奏って何?」を問うことになりました。4人の人たちが、別の楽器を使って、ひとつの音楽をどんな風に作り上げていくのか。それはまさに弦楽四重奏という合奏に取り組む4人の音楽家の「音楽観」を、言葉にしていく作業になりました。言葉にすることで、ふだん漠然と考えていたこと、知識としては持っていたけれど、人に語ったことはないことが整理されます。そして、ターゲットは小学一年生。
ぼくたちはクァルテットという名前がついていますが、これは4人の人たちがいっしょに音楽することです。で、どんな風に音楽を作っているかと言うと…
ここで登場するのが「かえるの歌」です。輪唱の定番曲を使って、Qセレシアの4人は見事にクァルテットで起こっていることを「実感」させることに成功しました。
Qセレシアは、「かえるの歌」を使って、どのように「弦楽四重奏」を実感させたのでしょうか?推理してみてください!
Qセレシアの答えは「レモネードブレイク」でお話しします。