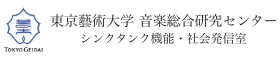音楽家の社会貢献と社会参画②(『若手音楽家のためのキャリア相談室24』)
箕口一美
「貢献」と「参画」
1. 個人の領域と、自分の社会的役割とのつながりとは
(本稿は2012年『ストリング』誌1月号に掲載された記事の改訂版となります。)
いささか個人的な話で恐縮ですが、3月11日の東日本大震災と今も続く原発災害が歴史に刻み込まれた2011年は、二人の父を喪った年として、決して忘れられない年になるでしょう。
家族は社会の最小単位である、と言いますが、ひとりの人間が、自分自身の延長として気を配ったり、心を砕いたり、優先順位をつけたりする広がりの最大単位を、家族と呼ぶのだ、というのが実感です。まるで映画「ゴッドファーザー」の世界のようだ、と思われるかも知れませんが、いわゆる「核家族」世代の中にぽっかり浮かぶ孤島のような「大家族」の中で育ってきて、それに反発もし、嫌悪さえ覚えて飛び出して30年余り。大家族の中心で、その枝にたくさんの人々を憩わせてきた大樹が遂に倒れ、混乱と山のような「社会的手続き」の中から、やっと母と弟、自分の連れ合いという新しい家族をスタートさせました。
その途上で、いままでは当たり前にように全力投球で来た、自分自身の社会的役割、仕事をしている人間としての役割に割くべき時間と労力(そして能力)を、家族という個人の領域のために使うことになりました。それがとても新鮮な経験だったのです。社会と個人の関係を鮮烈に意識できた、と言い換えてもいいでしょう。おいおい今更と言われそうな話ですが。
個人の領域と、自分自身の社会的役割の遂行とは、本来対立したり矛盾したりするものではない。もし、齟齬が起きるようなときには、何かバランスがおかしくなっていたり、社会側の要請に誤りがあったりする――そんな風に思ってきましたし、プライベートがこれほど多事多忙になってしまっている今も、そう思っています。音楽家という生き方をそば近くに見てきて、そんな風に思うようになったのでしょう。
音楽家という仕事は、ひとりの人間における社会の領域と個人の領域の関係が、一番分け隔てなくシームレスに繋がっています。自分自身が音楽に取り組む姿勢と思想が、そのまま社会におけるその人の使命(ミッション)と役割である――あるいは、そのように生きていくために一生精進し研鑽を積む生き方を選んでいる。私が心から音楽家を尊敬するのは、そういう生き方そのものが職業であるからなのです。
そんな大それた仕事じゃないよ、と言う方もいらっしゃるでしょう。でも、音楽家にあらざる人間の目には、10代の若者から90歳に届く大ベテランまで、あるべき音楽の姿を見つめる目で社会との関わりを見据えている、あるいはそれを目指して発展途上にある、と見えます。
2. 9/11の音楽家たち
少し古い話になりますが、9/11からほぼ1年という時期に、アメリカ東海岸を訪ねたときのことです。ある音楽院の学内誌が「9月11日の音楽家たち」を特集していました。その中の一人の学生の手記が、今でも記憶に残っています。
その日、マンハッタンにいた彼は、そのときあの島に居合わせてしまい、帰宅することも出来なかった多くの人々と同様、「今自分に出来ることは何か」と考え、とにかく現場に行ってみようとしました。もちろん既にロワーマンハッタンは立入禁止。ただ、そこで既にボランティアで動き出していた人から、消防士や警察官たちの臨時休息所に行って手伝って欲しいと言われ、指示された場所に駆けつけました。崩壊した二つのタワーの現場から、煤まみれのまま、一時の休憩をとる、たくさんの消防士や警察官たちの、身も心もボロボロになっている様子を見て、すっかり怯んでしまった彼は、しばらく何も出来なかったそうです。そのとき彼は自分が楽器を持ったままであることに気がつきました。そして、ほとんど何も考えないまま、ヴァイオリンを取り出し、調弦し、演奏を始めました。バッハでした。殺伐とした雰囲気と騒音に満ちていた場所に一丁のヴァイオリンの響きが少しずつ広がっていきました。1曲弾き終わったとき、そばでうずくまっていた消防士が、「もっと弾いてくれ」と言いました。彼は自分が弾けるレパートリーを弾き尽くし、耳にしたことのあるメロディやポップスまで、弾けそうなものはすべて動員して弾き続けました。薄暗い休息所の全体が見渡せたわけではないけれど、自分の演奏に耳を傾けている人がたくさんいることを彼は痛いほど感じました。ときおりわき上がる拍手に励まされて、どれくらいの長さ弾いていたかも覚えていないそうです。さすがに疲れ果てて、楽器を下ろしたとき、近くにいた煤まみれの男たちが、かすれた声で口々に「ありがとう」「よかったよ」「じんときたぜ」と言ってくれたことを、自分は一生忘れない、自分の演奏への賛辞としてではなく、音楽への深い感謝として・・・。
9/11は、音楽家と社会の関係を語るエピソードの宝庫です。日常のバランスを一瞬にして崩してしまうような一大事が起こったとき、音楽家は、音楽家であること自体が、社会での明確な役割を果たすことと直結してしまう事態に直面します。ある意味、音楽家に何が出来るか、わかりやすい場面が用意されてしまうのです。そんなときほど、音楽家であるあなた自身の普段からの姿勢が白日の下にさらされることもありません。
3. 音楽家の社会参画
2011年、3/11がこの国に生きる音楽家にとっての「9/11」になりました。
「貢献」という言葉に、上から目線を感じると言った人がいます。漢字が表している意味は、「貢ぐ」「献げる」ですから、上からどころか、他者のために与え尽くすことを指しています。なのに、どうしてそんな感じがしてしまうのでしょう。
ひとつには、他の人のために自分が行動する、という行為そのものに照れや「周りの人にどう思われるかしら」という一種の不安感を覚えてしまう、他人目線が酷く気になる最近のこの国の風潮が影響しているように思えます。それが昂じて「見ず知らずの他人に、自分の行為と身勝手な好意を押しつけることになるのでは」となり、遂には「貢献なんて言うことそのものが『上から目線』」と思うようになる・・・。
子供の頃に読んだことは忘れられない、特に意味が分からなかったことが忘れられないという癖があるもので、こういうときに必ず思い出してしまう聖書の一節があります。 「だから、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ(マタイによる福音書7:12)」
有名な「狭き門より入れ」という一節の直前に出てくる言葉で、「汝が欲することをなせ」とも訳されている部分です。
以前は「自分がやりたいようにしなさい」と読んで、聖書には「わがままはいけません!」と日頃言われていることと正反対のことが書いてあると、ちょっと喜んだり(なんてガキだ!)、でもどうして?と少しは素直に悩んだりしたものでした。
ひとりの人間が、社会にどんなふうに役に立てるのか、自分がどんな風に貢献できるのか、ということは、他の人が決めてくれる、指示してくれるわけではないのです。誰もあなたの代わりにあなた自身のことを決めてはくれません(もしそういう人がでてくるとしたら、その人は最終的にあなたを支配して、自分の奴隷にしようとしている、くらいに考えた方が無難です)。自分で想像力をいっぱい働かせることが大事。それでも他の人の気持ちが100%分かることはなくて、最後に行き着くのが「自分がその立場だったら、そんな境遇に置かれたら、何をして欲しいと思うだろうか」ということを思い巡らすことです(聖書研究家ではないので、これはあくまで、子供の頃の自分への50代の自分からの答えです)。
自分が音楽家として、この社会に何が出来るか、何をすべきなのかを考えることは、自分自身のミッション・ステートメント、即ち、人生のぶれない軸を自分の中に定めることです。音楽という芸術が、それに耳を傾けてくれる他者(=聴き手)なしには成立しない、という本質に立ち戻ってみても、音楽家が社会貢献を考えるのは、とても自然なこと。社会「参画」という言葉は、自分はこういう姿勢で社会に関わると決めたあなたが、それを実際に行動に移すことを示しています。
音楽を演奏することで、あるいは教えることで、自分は次の世代に何かを伝えることをミッション(使命)だと思った。では、次にそれをどんなふうに実現させるか。貢献と参画はセットです。そして、思いを行動に移すときには、またまたたくさんの想像力を働かせて、自分の創造力(つくり出す力)を駆使する必要があります。
ピアニストの田村緑さんが、学校の音楽の時間に行うアウトリーチプログラムを作っていく過程が、まさにそれでした。
イギリスの音楽大学で学んだ田村さんは、寄宿先の奥さんが家で催すお茶会でピアノを弾くうちに、そういう身近で親しい関係のなかで演奏することに喜びを見いだすようになりました。弾く人から聴く人への一方通行ではない関係、競争や比較のために演奏するのではなく、音楽を楽しむために演奏がある時間。これだ、これが音楽することだ、と思った田村さんが、日本に戻ってからその情熱を注ぎ込んだのが、アウトリーチでした。お茶会で楽しむように音楽に出会えば、ずっと音楽が好きでいてくれるだろう・・・ピアノのそばで、響きが生まれる仕組みを説明しながら、響板の特性からハンマーの素材まで、こどもたちが実感できるような仕掛けをあれこれ考え出したり、音楽が伝える思いや表現に近づいてもらうために、国語の教科書にでている詩をこどもと一緒に朗読しながら、自然に音楽に入っていったり。こどもたちが楽しく音楽と出会っていくための工夫は今もどんどん進化しているとか。
その原点は「幸せに音楽することのできたお茶会で発見した、音楽の幸せな姿を伝えたい」という、「彼女が欲したこと」。それを他の人にも知って欲しい、共感して欲しいと思うことがミッションの自覚となり、音楽家として社会と関わっていく原動力になりました。その思いを行動に移すための最良の仕掛けとして、田村さんはアウトリーチという場面に、自分の創造力と想像力を駆使しています。この人と仕事をしていると、再現芸術としてのクラシック音楽は、本当に豊かな創造力を持っている、と実感させてもらえます。
音楽家の社会貢献と社会参画は、何か一大事が起こったときにだけ発揮されるものではありません。音楽家であることそのものが、いつもそうした姿勢を必要としています。
次回は「好きなことを仕事にしている」ことを巡って、考えてみたいと思います。